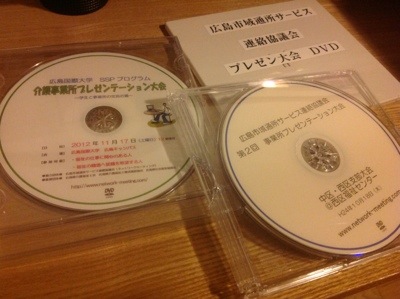僕の周りの介護の職に就く20代~30代の人達の
口からでる悩みの多くは、『将来が不安だ』で、
いわゆるキャリアデザインが出来ないということだ。
一般のサラリーマンでも、それはなかなか出来る事ではないが…
正社員で働く介護職たちは、概ね専門学校や大学で福祉・介護を学び、
社会福祉士や介護福祉士を取得し現場に入る。
しかし、名称独占である資格に加え、高齢者の生活を支える業務という側面から、
未だ資格的な学習よりも生活経験が優先して効果を発揮される現場業務では、
なかなか若者達が、その資格を活かした業務が出来ていない実情がある。
通所サービスでは前述の資格を有する者で配置しなければならない
『生活相談員』という職務や、介護福祉士を保持する職員の割合などで
算定出来る加算などもあり、事業者は資格保有者の確保に懸命にはなるが、
それは事業的な部分であり、
個人の業務の部分で資格が活かされる職務があるとはいえない。
一般的に介護業界で『キャリアアップ』とされて謳われているのは、
ヘルパー(現初任者研修)⇒介護福祉士⇒介護支援専門員(ケアマネージャー)
という資格取得ルートだが、これも全ての資格合格者がケアマネージャーの職に
就けるわけではないし、ケアマネージャーの先の業務に関して、
見えるものがないという意味ではルートは途切れている。
我々協議会が活動していく上で、主眼としていることは
『キャリアデザインが出来る介護現場の構築』だ。
そもそも介護=身体生活援助(排泄・入浴・食事)だけでは無い。
精神生活援助を行ってこそ、介護=福祉で、時代に合ったサービス提供の
模索が行われなければならないが、介護保険制度という公定価格の中で行う
事業である中、事業者の裁量で出来るサービスも限界が有ることは事実だ。
属する事業者(民間企業、社会福祉法人、医療法人、NPO)により、
求めるものも違う。
だからこそ『何処で働くか?』を主体的に探すことができる環境を整えることが
『キャリアデザイン』を考える上で重要な作業になる。
③に続く。